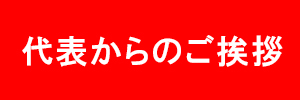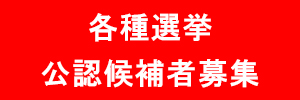はじめに
私たちは「衰退する未来」を、ただ受け入れるしかないのか?
いま、日本は歴史的な岐路に立たされています。私たちの目の前には、避けることのできない「人口が急激に減っていく」という現実があります。このままいけば、2070年には日本の人口は今より3割も少ない8700万人になり、社会は超高齢化の波に飲み込まれる。これは国の研究所が出した、れっきとした予測です¹。社会保障は?インフラは?そして、この国の活力そのものは、一体どうなってしまうのでしょうか。この厳しい現実から目をそらすかのように、「日本人ファースト」を掲げ、外国人を排除すれば大丈夫だ、という声が大きくなっています。しかし、本当にそうでしょうか?
この記事は、そうした感情論ではなく、世界中のデータと研究に基づき、日本の未来を真剣に考えるための「設計図」です。そして、私たちが導き出した結論は、極めて明確です。
戦略的に移民を受け入れることは、もはや「選択肢」ではなく、この国が生き残り、豊かさを維持するための「唯一の現実的な道」である、ということです。
この記事では、まず「外国人を排除する」という考え方が、歴史的に見ていかに高くつく選択だったかを見ていきます。そして、データを用いて、移民が経済にどれほどのプラスの影響を与えるのかを具体的に解き明かします。
その上で、今の日本の制度がいかに機能不全に陥っているかを分析し、世界の国々の成功と失敗から、私たちが学ぶべき教訓を探ります。最終的に、これからの日本のための、具体的で、すぐにでも始められる政策プランを提案します。
これは、衰退という未来をただ受け入れるのか、それとも多様性という新しい力で、ダイナミックな未来を自ら創り出すのか。私たち一人ひとりに突きつけられた、重要な問いかけなのです。
第I部
グローバルな排外主義の潮流とその歴史的ルーツ
現代の移民を巡る議論は、日本だけで起きているわけではありません。それは、世界的に広がる大きなうねりの中にあります。
トランプ現象と「小トランプ」たちの誕生
この流れを決定づけたのは、2016年のアメリカ大統領選挙でのドナルド・トランプ氏の勝利、そして2024年の再選でした。彼は、選挙に勝つために移民を「侵略者」「犯罪者」と呼び、排外的な言葉を政治のど真ん中に持ち込みました¹⁰。このやり方は、世界中に伝染します。ブラジルのボルソナロ元大統領、イギリスのボリス・ジョンソン元首相、そして日本でも見られる立花孝志氏や神谷宗幣氏といった人々。彼らは皆、トランプ氏の手法を真似て、人々の不安を煽り、支持を集めようとしています。
アメリカ史に刻まれた「排斥」のパターン
しかし、こうした動きは、決して新しいものではありません。特に「移民の国」アメリカの歴史は、皮肉にも、新しくやってくる人々を拒絶し、排斥してきた歴史でもあるのです¹¹。
- 始まりは「白人限定」だった:アメリカで最初に作られた市民権の法律(1790年)は、市民になれる人を「自由な白人」に限定していました。国の始まりから、人種による「排除の論理」が組み込まれていたのです¹²。
- 時代ごとに変わる「敵」:憎悪の対象は、時代と共に変わりました。18世紀にはドイツ系移民が、19世紀にはアイルランド系カトリック教徒が、そして20世紀初頭には中国系や日系移民が、「文化を壊す」「仕事を奪う」脅威と見なされ、激しい差別の対象となったのです¹¹⁻¹²。
- 法律でアジア人を締め出した時代:20世紀に入ると、優生学という誤った科学思想の影響もあり、南・東ヨーロッパやアジアからの移民を「劣った人種」と決めつけ、1924年の移民法(ジョンソン・リード法)では、アジアからの移民を完全に禁止してしまいました¹²。
この歴史が教えてくれるのは、経済が不安定になると、決まって移民がスケープゴートにされ、社会の不満の「ガス抜き」に使われてきた、という悲しいパターンです¹³。今の世界的な排外主義の広がりは、この古い脚本が、SNSとポピュリスト政治家によって、現代版として再演されているに過ぎないのです。
第II部
「日本人ファースト」が招く、高くつく代償
排外主義は、「国民の利益を守る」という耳障りの良い言葉で語られます。しかし、歴史を振り返れば、特定のグループを排除する政策が、長期的には国そのものに深刻なダメージを与えてきたことは明らかです。それは、人的資本という最も大切な資産を自ら破壊し、イノベーションを止め、国際社会で孤立する「高くつく自傷行為」に他なりません。
ナチス・ドイツで失ったもの
その最も悲劇的な例が、ナチス・ドイツです。1933年以降、反ユダヤ主義政策によって、アインシュタインをはじめとする多くのユダヤ系の優秀な科学者や専門家たちが、大学や公職から追放されました¹⁴。その数は大学教授の15%以上にのぼり、中には後にノーベル賞を受賞する科学者が20人も含まれていたのです¹⁴。この「頭脳流出」の代償は、計り知れません。最近の研究では、優秀なユダヤ人専門家を失った地域で育った子供たちは、大人になってからの学歴が低くなる傾向があったことが分かっています¹⁴。特定のグループを排除することは、社会全体の知的活力を奪い、次の世代の可能性までをも蝕んでしまうのです。
ブレグジットが英国に突きつけた請求書
もっと最近の例では、2016年のイギリスのEU離脱(ブレグジット)があります。これは、「移民を制限し、国境を取り戻す」というスローガンが、経済合理性に打ち勝ってしまった大規模な社会実験でした。その結果はどうだったでしょうか。イギリス政府自身の予測でも、ブレグジットによって国の生産性は長期的に4%低下し、貿易の規模は15%も縮小するとされています¹⁵。実際、企業の投資は停滞し、経済は低迷。その穴埋めのために、イギリス政府は日本円にして約7.8兆円もの大規模な増税をせざるを得なくなりました¹⁶。
表1:排外主義的政策の経済的帰結
| 政策・出来事(年) | 国 | 対象集団 | 掲げられた大義名分 | 主要な経済的帰結(定量的) |
|---|---|---|---|---|
| 職業官吏再建法 (1933) | ナチス・ドイツ | ユダヤ系専門職 | アーリア人種の純粋性、国民共同体の保護 | ・大学教授の15%以上が追放 ・追放地域で育った世代の平均就学年数が有意に低下¹⁴ |
| アジア人追放 (1972) | ウガンダ | インド・パキスタン系住民 | 経済のウガンダ人化 | ・商業・工業部門の崩壊 ・1987年までにアフリカで最も低い経済成長率の一つに転落¹⁷ |
| ブレグジット (2016) | 英国 | EU市民 | 国境管理の回復、主権の回復 | ・2030年までにGDPがEU残留時比で5%以上減少(OECD予測)¹⁸ ・長期的な生産性が4%低下、貿易量が15%低下(OBR想定)¹⁵ ・生産性低下により約400億ポンドの増税が必要¹⁶ |
第III部
経済のエンジン:データが語る移民の真の価値
「移民は仕事を奪い、税金にタダ乗りする」――。これは、排外主義的な主張の定番ですが、世界中の経済学研究が積み重ねてきたデータは、この「神話」が全くの誤りであることを証明しています。
イノベーションと新しいビジネスは、移民が運んでくる
移民は、ただの働き手ではありません。新しいアイデアやビジネスを生み出す、きわめて重要な「触媒」なのです。アメリカの研究によると、発明家全体に占める移民の割合は16%に過ぎないのに、なんと全特許の23%は移民によって生み出されていました²。しかも、彼らが生み出す特許は、経済的な価値も質も高いことが分かっています²。さらに驚くべきは、優秀な移民がアメリカ生まれの研究者とチームを組むと、そのアメリカ人研究者の生産性まで上がるという「波及効果」です。これを全部合わせると、アメリカのイノベーションの36%は移民の貢献によるもの、と試算されているのです¹⁹。
表2:米国のイノベーションに対する移民の貢献度(1990年~2016年)
| 指標 | 移民の割合 | ネイティブの割合 |
|---|---|---|
| 発明家人口に占める割合 | 16% | 84% |
| 特許に占める割合 | 23% | 77% |
| 特許被引用数に占める割合 | 25% | 75% |
| 特許の経済価値に占める割合 | 25% | 75% |
| 総貢献度(直接効果+波及効果) | 36% | 64% |
| 出典:NBERワーキングペーパーからのデータを統合² |
ビジネスの世界でも同じです。アメリカでは起業家の4人に1人が移民²⁰。カナダでも、移民のほうがカナダ生まれの人よりも起業する確率が高く、新しく生まれる雇用の25%は移民が作った会社によるものです²¹。
経済を大きくし、生産性を高める力
移民は、働く人を増やすことで、経済全体のパイを大きくします。カナダでは、2010年代の労働力増加の84%が移民によるものでした²²。国際通貨基金(IMF)の研究では、移民が1%増えると、5年後には国の総生産(GDP)が約1%増える、という結果が出ています³。もっと大事なのは、国民一人当たりのGDPも増える、という点です。これは、移民が単に人口を増やすだけでなく、経済全体の効率性を高めている証拠に他なりません³。
税金を払い、社会を支える人々
「移民は福祉にタダ乗りする」という主張は、本当なのでしょうか? 長い目で見れば、答えは「ノー」です。
アメリカの科学アカデミーの研究によると、カギを握るのは「学歴」と「移住した時の年齢」です⁴。若くして移住し、大学以上の教育を受けた移民は、生涯で受け取る公的サービスよりもはるかに多くの税金を国に納める「純貢献者」となります⁴。特に大学院卒の移民の場合、生涯で100万ドル(約1億5000万円)以上も国に貢献する可能性があるのです²³。そして、さらに重要なのは、彼らの子供たち、つまり「移民二世」です。彼らは、アメリカ社会で最も国に貢献しているグループの一つなのです⁴。これは日本にとっても他人事ではありません。あるシミュレーション研究では、働く世代の移民を受け入れることが、日本の年金制度の負担を劇的に軽くする、という結果が出ています²⁴。
表3:移民の生涯純財政貢献度の比較(米国における推計)
| 人口集団 | 学歴 | 生涯純財政貢献度(連邦) | 生涯純財政貢献度(州・地方) | 生涯純財政貢献度(合計) |
|---|---|---|---|---|
| 第一世代移民 | ||||
| 大学院卒 | +$899,000 | +$151,000 | +$1,050,000 | |
| 大卒 | +$426,000 | +$109,000 | +$535,000 | |
| 高校卒 | +$10,000 | -$100,000 | -$90,000 | |
| 高校中退 | -$232,000 | -$198,000 | -$430,000 | |
| 第二世代 | 平均 | +$259,000 | +$30,000 | +$289,000 |
| 第三世代以降(国内生まれ) | 平均 | -$22,000 | -$34,000 | -$56,000 |
| 注:米科学アカデミー(NAS)およびケイトー研究所の報告書²⁵に基づく代表的な推計値。 |
第IV部
なぜ日本は失敗しているのか? 機能不全の外国人管理システム
これほど多くのメリットがあるにもかかわらず、なぜ日本では外国人材が活かされていないのでしょうか。その答えは、国の根本的な姿勢にあります。「移民政策はとらない」という建前と、人手不足を補うために外国人を受け入れ続ける現実。この大きな矛盾が、日本の制度を歪めているのです。
搾取の温床:「技能実習」という名の虚構
外国人技能実習制度。名前は立派ですが、その実態は「国際貢献」とは名ばかりの、安価な労働力を確保するための仕組みでした⁶。この制度の最大の問題は、働く人が原則として「職場を自由に変えられない」という点にあります。これが、弱い立場の実習生に対する、賃金未払いや長時間労働、時には暴力といった深刻な人権侵害を生む温床となってきました²⁶。政府はこの制度を見直し、「育成就労制度」という新しい名前の制度を作ろうとしています。しかし、職場を移ることに依然として制限が残るなど、根本的な問題は解決されておらず、「看板を付け替えただけ」という厳しい批判が国内外から上がっています²⁷。
拒絶の砦:閉ざされた日本の難民制度
日本の難民庇護制度は、国際的に見ても異常な状態です。2022年、日本が難民として認めた人の割合は、わずか0.7%。カナダやイギリスでは60%以上の人が認められているのとは、比べものになりません⁷。なぜ、これほどまでに低いのでしょうか。 第一に、難民条約の解釈が極端に厳しいこと²⁸。第二に、審査を、国境管理を仕事とする出入国在留管理庁(入管)が行っており、独立した第三者機関が存在しないこと²⁹。そして第三に、裁判所の令状もなしに、いつ終わるとも分からないまま入管施設に収容される「無期限収容」という、非人道的な扱いがあることです²⁹。これらの制度は、外国人を「社会の一員」としてではなく、一時的な「管理対象」としてしか見ていない、という日本の根本的な姿勢の表れなのです。
第V部
世界の国々から学ぶ、統合と共生の形
多文化社会への道は一つではありません。世界の国々は、それぞれの歴史や文化の中で、様々な試行錯誤を繰り返してきました。その成功と失敗は、これからの日本にとって、大きなヒントを与えてくれます。
積極的な統合を目指す国:カナダ
カナダは、世界で初めて「多文化主義(マルチカルチュラリズム)」を国の公式なポリシーにした国です。多様性は、克服すべき課題ではなく、国を豊かにする「資産」だと考えているのです³¹。その政策は非常に戦略的です。国の経済にとって必要なスキルを持つ人をポイント制で選ぶ「経済移民」を中心に、手厚い言語教育や就労支援で、新しい移民がスムーズに社会に溶け込めるようサポートしています³²。その結果、移民はカナダ経済の重要な担い手となり、カナダ生まれの人よりも高い確率で起業するなど、大きな成功を収めてきました²¹⁻²²。しかし、そんなカナダでさえ、近年は大きな壁にぶつかっています。急激に移民を増やしすぎた結果、住宅価格が異常なまでに高騰し、医療や教育といった社会サービスが追いつかなくなっているのです³⁵⁻³⁶。
日本への教訓:カナダの経験は、計画的な移民政策がいかに有効かを示しています。しかし同時に、住宅やインフラといった国内の政策としっかり連携させなければ、どんなに良い制度も国民の支持を失ってしまう、という重要な警告でもあるのです³⁷。
管理によって共生を目指す国々:シンガポールとマレーシア
- シンガポール:この国は「多民族主義」という独自の方法をとっています。最も特徴的なのは、HDBと呼ばれる公営住宅で、団地ごとに中国系、マレー系、インド系といった民族の割合に上限を設けていることです³⁹。これにより、特定の民族だけが固まって住む「ゲットー化」を防ぎ、異なる民族が日常的に隣人として暮らす環境を強制的に作り出しています。社会の安定には大きく貢献しましたが、住む場所を自由に選べないという代償も伴います³⁸。
- マレーシア:ここでは、人口の多数を占めるマレー系を優遇する「アファーマティブ・アクション」が政策の根幹です⁴⁰。これは、歴史的な経済格差を是正し、社会を安定させる目的がありましたが、一方で、中国系やインド系の国民の不満を招き、優秀な人材が国を去る「頭脳流出」の原因にもなっています⁴¹。
ヨーロッパからの教訓:ドイツ
長年「うちは移民の国ではない」と言い続けてきたドイツも、近年は現実と向き合い、大規模な統合政策に乗り出しました⁴²。特にメルケル元首相の時代には、多くの難民を受け入れ、彼らが社会の一員となれるよう、手厚い支援を行いました⁴⁴。職業資格の相互承認を進めるなど、経済的な貢献への道を開いた点は高く評価されています⁴⁵。しかし、その一方で、多くの移民に義務付けられている「統合コース」(ドイツ語や市民教育の講座)は、「失敗」と評されることが少なくありません⁴⁶。やる気のない参加者、レベルの合わない授業、そして託児所不足…。問題は山積みです。
日本への教訓:ドイツから学ぶべき最も重要なことは、「政策の失敗」の責任が、いつの間にか「統合しようとしない移民」のせいにされてしまう、「責任転嫁の構造」です⁴⁶。トップダウンで画一的な義務を押し付けるだけでは、多様な背景を持つ人々の現実に寄り添うことはできないのです。
第VI部
世界の視点から考える:なぜ人々は故郷を離れるのか?
受け入れ国の政策を考えるだけでは、問題の半分しか見ていません。そもそも、なぜ人々は危険を冒してまで、住み慣れた故郷を離れなければならないのでしょうか。その根本原因、つまり送り出す国々の「プッシュ要因」に取り組まない限り、移住の流れが止まることはありません⁴⁷。
「援助すれば移住は減る」という単純なウソ
「貧しい国にお金やモノを援助すれば、移住してくる人は減るだろう」。一見、正しく聞こえますが、現実はもっと複雑です。「援助と移住のパラドックス」という言葉があるように、最貧国が少し豊かになり始めると、むしろ国外へ移住する人は一時的に増える傾向があるのです⁴⁸。これは、援助の目標を考え直す必要があることを示しています。短期的に移住を止めることではなく、人々が「自分の国に留まりたい」と心から思えるような、安定的で公正な社会を築く手助けをすること。それこそが、本当の意味での根本解決に繋がるのです。そのためには、道路や港を作るといったインフラ支援だけでなく、その国の「ガバナンス(統治能力)」、つまり、法の支配や汚職防止といった、国の仕組みそのものを強化する支援が不可欠です⁴⁹。
幸い、絶望的な状況からでも、見事なガバナンス改革を成し遂げた国は存在します。
- ボツワナ:アフリカの「奇跡」とも呼ばれるこの国は、独立以来、汚職を非常に低いレベルに抑えることに成功してきました。その秘訣は、トップの強い意志、政治から独立した公務員制度、そして強力な権限を持つ汚職対策機関にあります⁵⁰。
- ルワンダ:1994年の悲惨なジェノサイドの後、カガメ政権は徹底した汚職対策と公務員制度改革で、驚異的な経済成長を成し遂げました⁵¹⁻⁵⁵。その権威主義的な手法には批判もありますが、国家再建の一つのモデルを示しています。
- ジョージア(2004年~2013年):2003年の「バラ革命」後、当時世界で最も腐敗した国の一つだったジョージアは、急進的な改革を断行しました⁵⁶。腐敗の温床だった交通警察を全員解雇して作り直し、税の種類を大幅に減らし、許認可の84%を撤廃するなど、役人が賄賂を要求する「機会」そのものを徹底的に奪ったのです⁵⁶。しかし、この成功は過去のものとなりつつあります。近年の政権は親ロシア的な姿勢を強め、民主主義が後退しており、安定した制度がいかに重要かという教訓を残しています⁵⁷。
第VII部
これからの日本のための政策設計図:「外国人労働者」から「共に生きる社会」へ
これまでの分析を踏まえ、日本の未来のための、具体的で実行可能な政策プランを提案します。
基礎改革:搾取から、共に生きる社会へ
- 時代遅れの制度は、今すぐ廃止を:技能実習制度や育成就労制度といった、人権侵害の温床となってきた制度は完全に廃止し、労働者としての権利を保障する、透明性の高い労働許可制度に切り替えるべきです⁶。
- 「移民受け入れ国」としての新たな出発:日本は「移民受け入れ国」であることを明確に宣言し、長期滞在や永住、国籍取得への、分かりやすく公平なルールを作る必要があります。カナダのポイント制を参考に、日本の社会や経済が必要とする人材を戦略的に受け入れていきましょう⁸。
- 難民保護を、国際基準に:難民認定の審査は、入管から独立した新しい機関が担うべきです。そして、国際人権法に反する「無期限収容」は法律で禁止しなければなりません⁹。
社会のインフラを、多文化仕様にアップデートする
- 教育:ドイツの失敗に学び、画一的ではない、柔軟な日本語教育プログラムを公的に提供します。また、すべての子どもたちが多様性を尊重する心を育めるよう、多文化共生教育を学校のカリキュラムに導入します⁴⁶。
- 医療・福祉:在留資格にかかわらず、誰もが安心して医療を受けられるよう、国民健康保険への加入を徹底します。また、言葉の壁を取り除くため、公的な医療通訳の制度を全国に広げます⁵⁸。
- 雇用・住居:国籍や人種を理由に、仕事や住まい探しで不当な差別を受けることがないよう、実効性のある罰則を伴った「人種差別禁止法」を制定します。
安心できる社会を、みんなでつくる
- データで「誤解」を乗り越える:「移民が増えると犯罪が増える」という主張は、多くの場合、事実に反します。カナダでは、移民のほうが暴力犯罪の被害に遭う率が低い、という統計さえあります⁵⁹。こうした客観的なデータを、政府が積極的に国民に示していくことが重要です。
- 信頼で築く地域の安全:警察と外国人コミュニティとの信頼関係を築くため、警察の仕事と入管の仕事を明確に分ける「ファイヤーウォール・ポリシー」の導入を進めます。これにより、たとえ非正規滞在者であっても、犯罪に巻き込まれた時に、強制送還を恐れずに警察に相談できる社会を目指します⁶⁰。
- 顔の見える関係をつくる:政府は移民が社会に貢献している姿を積極的に広報し、地域レベルでの文化交流イベントなどを支援することで、日本人と外国人がお互いを知り、理解し合う機会を増やしていきます⁶¹。
表4:移民と国内生まれの人口における犯罪・治安関連指標の比較(カナダ)
| カテゴリ | 移民人口 | 国内生まれ人口 |
|---|---|---|
| 暴力犯罪被害率(人口1,000人当たり) | 68件 | 116件 |
| 暴力犯罪被害に遭うリスク(リスク要因調整後) | 国内生まれ人口より30%低い | – |
| 警察に対する肯定的な評価 | 国内生まれ人口より高い傾向 | – |
| 出典:カナダ統計局の報告書⁵⁹ |
第VIII部
結論:私たちはどちらの未来を選ぶのか
この記事を通じて、私たちはデータと世界の事例に基づき、排外主義がいかに危険で、移民受け入れがいかに大きな利益をもたらすかを見てきました。結論は、きわめてシンプルです。
排外主義は、国を衰退させる「自滅の道」です。そして、移民は成長の「エンジン」であり、多様性は私たちの「力」になるのです。
今、私たち日本人に問われているのは、このまま過去の延長線上で緩やかに衰退していく未来をただ受け入れるのか、それとも、多様性という新しいエネルギーを取り込んで、ダイナミックで強い未来を自らの手で創り出すのか、という根本的な選択です。もちろん、改革への道は簡単ではありません。最大の壁は、政治です。アメリカのマルコ・ルビオ国務長官の例は、私たちに痛烈な教訓を教えてくれます。彼はかつて、党派を超えて、現実的な移民改革を目指すリーダーの一人でした。しかし、党内の排外主義的な声に抗しきれず、ついにはかつての自分の理念を捨て、強硬な排外主義者に変貌してしまったのです⁶²。国家の長期的な利益よりも、目先の政治的な生き残りを優先してしまう。この悲劇を、日本で繰り返してはなりません。
外国人との共生は、もはや綺麗事や人道的な問題だけではありません。それは、少子高齢化という厳しい現実の中で、この国の豊かさと活力を守り抜くための、最も現実的で、唯一の希望ある戦略なのです。
排外主義という過去の亡霊に別れを告げ、勇気をもって未来への扉を開く。その時が、今、来ています。
引用文献
- 国立社会保障・人口問題研究所R5推計:2070年の総人口は3割減少8700万人の見通し. (https://www.satsuki-jutaku.mlit.go.jp/journal/article/p=2245)
- The Contribution of High-Skilled Immigrants to Innovation in the United States. NBER. (https://www.nber.org/papers/w30797)
- The Macroeconomic Effects of Large Immigration Waves. IMF. (https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2023/12/14/The-Macroeconomic-Effects-of-Large-Immigration-Waves-542526)
- Economic and Fiscal Impact of Immigration. National Academies. (https://www.nationalacademies.org/our-work/economic-and-fiscal-impact-of-immigration)
- 研究者の多様性が特許出願行動に与える影響の定量分析. RIETI. (https://www.rieti.go.jp/jp/publications/nts/16j004.html)
- 技能実習生の問題とは?制度の矛盾・失踪・人権侵害の実態と企業が取るべき対策. (https://www.careerlinkfactory.co.jp/blog/technical-intern-trainee-problem/)
- 日本の難民認定率は?世界の国々と比較してみよう. gooddo. (https://gooddo.jp/magazine/peace-justice/refugees/japan_refugees/3913/)
- 移民政策と政府間関係. (https://www.chihou-zaimu.com/library/5ca2ad437d7406de239adce7/636b660d063fac70f1ebdccd.pdf)
- 難民・収容・送還に関する、日本政府に対する勧告一覧. 難民研究フォーラム. (https://refugeestudies.jp/wp/wp-content/uploads/2022/03/UNRecommendations_RSF_2203.pdf)
- 米国における新保守「ニュー・ライト」. Marubeni. (https://www.marubeni.com/jp/research/report/data/MWR_2025_14NewRIght20250610.pdf)
- The Long History of Xenophobia in America. Tufts Now. (https://now.tufts.edu/2020/09/24/long-history-xenophobia-america)
- “Other”: A Brief History of American Xenophobia Supplementary Timeline. Densho. (https://densho.org/wp-content/uploads/2021/11/Xenophobia-Video-Supplemental-Timeline.pdf)
- Xenophobia & Anti-Immigrant Extremism: From Fringe to Mainstream. Human Rights First. (https://humanrightsfirst.org/library/xenophobia-fact-sheet/)
- The long-term direct and external effects of Jewish expulsions in Nazi Germany. EconStor. (https://www.econstor.eu/bitstream/10419/51695/1/669696331.pdf)
- How are our Brexit trade forecast assumptions performing?. Office for Budget Responsibility. (https://obr.uk/box/how-are-our-brexit-trade-forecast-assumptions-performing/)
- THE ECONOMIC IMPACT OF BREXIT, NINE YEARS ON: WAS THE CONSENSUS RIGHT?. The Constitution Society. (https://consoc.org.uk/wp-content/uploads/2025/06/The-Economic-Impact-of-Brexit.pdf)
- アジア人追放事件 (ウガンダ). Wikipedia. (https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E4%BA%BA%E8%BF%BD%E6%94%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6_(%E3%82%A6%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%80)
- The Economic Consequences of Brexit. OECD. (https://www.oecd.org/en/publications/the-economic-consequences-of-brexit_5jm0lsvdkf6k-en.html)
- The Contribution of High-Skilled Immigrants to Innovation in the United States. NBER. (https://www.nber.org/papers/w30797)
- Immigrants Drive More Innovation than U.S.-born Counterparts. Boundless. (https://www.boundless.com/blog/immigrant-innovation-study/)
- Immigrant entrepreneurship in Canada. BDC.ca. (https://www.bdc.ca/en/articles-tools/blog/immigrant-entrepreneurship-taking-centre-stage-canada)
- 移民政策と政府間関係. (https://www.chihou-zaimu.com/library/5ca2ad437d7406de239adce7/636b660d063fac70f1ebdccd.pdf)
- The Lifetime Fiscal Impact of Immigrants. Manhattan Institute. (https://manhattan.institute/article/the-lifetime-fiscal-impact-of-immigrants)
- Impacts of Immigration on Japanese Economy: An investigation with a computable OLG model. (https://cis.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/society/oguro110302.pdf)
- The Fiscal Impact of Immigration in the United States. Cato Institute. (https://www.cato.org/white-paper/fiscal-impact-immigration-united-states)
- 主張/技能実習生新制度/これでは人権侵害を防げない. 日本共産党. (https://www.jcp.or.jp/akahata/aik23/2024-03-09/2024030902_01_0.html)
- 外国人技能実習制度の見直し:人権保護を最優先に選ばれる日本に. (https://www.nri.com/jp/media/column/kiuchi/20231124_2.html)
- はじめに 1.日本の難民認定制度の現状概観. (https://refugeestudies.jp/wp/wp-content/uploads/2020/08/The-Situation-and-Problems-with-the-Refugee-Recognition-Procedure-in-Japan-Revisited.pdf)
- <3分で分かる>難民問題、日本の現状と課題 私たちにできることは?. ボーダレス・ジャパン. (https://www.borderless-japan.com/words/refugee/)
- カナダの移民政策及びその主要都市への影響. (https://www.clair.or.jp/j/forum/series/pdf/50.pdf)
- 移民政策と政府間関係. (https://www.chihou-zaimu.com/library/5ca2ad437d7406de239adce7/636b660d063fac70f1ebdccd.pdf)
- カナダ:移民受け入れ先進国が直面する問題. 大和総研. (https://www.dir.co.jp/report/research/economics/japan/20141119_009154.pdf)
- 2021年カナダ国勢調査、移民割合が建国以来最高の23%に. ジェトロ. (https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/11/00b4dec08b455955.html)
- カナダの2021年国勢調査、労働力の高学歴化や技能職不足などが顕著に. ジェトロ. (https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/12/24fb30d20a10cf67.html)
- カナダ各州の2024年経済見通し. (https://visajpcanada.com/column/blog-20231109/)
- Column: オタワ便り NO.33 (2025年1月). 日加協会. (https://www.nikkakyokai.org/columns/2025/202501/202501column.html)
- カナダにおける移民政策の再構築. (https://iminseisaku.org/top/pdf/journal/004/004_002.pdf)
- Multiculturalism in Singapore: An Instrument of Social Control. ResearchGate. (https://www.researchgate.net/publication/249741264_Multiculturalism_in_Singapore_An_Instrument_of_Social_Control)
- Chen, Harrison — “Singapore’s Ethnic Integration Policy: The Key to a Racially Harmonious Society?”. (http://classic.austlii.edu.au/au/journals/UNSWLawJlStuS/2019/2.html)
- Multicultural Policies in Malaysia: Challenges, Successes, and the Future. (https://gjia.georgetown.edu/2024/06/01/multicultural-policies-in-malaysia-challenges-successes-and-the-future/)
- A Revision of Malaysia’s Racial Compact. Harvard Political Review. (https://harvardpolitics.com/a-revision-of-malaysias-racial-compact/)
- 第 11 章 「移民国」ドイツにおける反イスラームと文化の問題. (https://www2.jiia.or.jp/pdf/research/H29_Global_Risk/11_ishikawa.pdf)
- ドイツが難民の受け入れに積極的な理由. (https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/mhri/research/pdf/insight/eu151007.pdf)
- アンゲラ・メルケル前ドイツ首相、2022年UNHCRナンセン難民賞を受賞. UNHCR. (https://www.unhcr.org/jp/49463-pr-221004.html)
- ドイツの移民・難民政策の新たな挑戦. (https://jcie.or.jp/data/media/Publication/402/2016GermanReport.pdf)
- ドイツの移民政策における「統合の失敗」. 東京大学ドイツ・ヨーロッパ研究センター. (https://www.desk.c.u-tokyo.ac.jp/download/es_8_Kobayashi.pdf)
- Background paper1 Theme 3: Good migration governance for sustainable development. (https://www.gfmd.org/sites/g/files/tmzbdl1801/files/documents/final_gfmd_2018_rt_session_3.1_background_paper.pdf)
- Deterring Emigration with Foreign Aid: An Overview of Evidence from Low-Income Countries. (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7413619/)
- Preventing Corruption A Compendium of Global Case Studies. CIPFA. (https://www.cipfa.org/services/cipfa-supports/fraud-and-corruption/preventing-corruption-a-compendium-of-global-case-studies)
- Tackling Corruption in Commonwealth Africa: Case Studies of Botswana, Lesotho, Mauritius, Rwanda and Seychelles. (https://www.thecommonwealth-ilibrary.org/index.php/comsec/catalog/download/877/877/7358?inline=1)
- ルワンダ内戦. 世界史の窓. (https://www.y-history.net/appendix/wh1703-105.html)
- Reforming the Ranks: Public Service Reform in Post-Genocide Rwanda. Princeton University. (https://successfulsocieties.princeton.edu/sites/g/files/toruqf5601/files/Policy_Note_ID163.pdf)
- Rwanda’s impressive performance is instead agency-based and results from the deliberate actions of its President, Paul Kagame. (https://www.againstcorruption.eu/wp-content/uploads/2021/02/ERCAS-Working-Paper-n.-64-Rwanda-Michela-Pellegatta.pdf)
- The Rwandan government formulates and implements its anti-corruption efforts via donors’ governance support and homegrown initiatives. (https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/aeds-03-2017-0028/full/html?utm)
- Rwanda’s development model wouldn’t work elsewhere in Africa. (https://qz.com/africa/1175371/rwanda-and-paul-kagames-development-model-wouldnt-work-elsewhere-in-africa)
- Economy of Georgia (country). Wikipedia. (https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Georgia_(country)
- Why Georgia’s Democracy Is Collapsing. Journal of Democracy. (https://www.journalofdemocracy.org/online-exclusive/why-georgias-democracy-is-collapsing/)
- 多文化共生事例集. 総務省. (https://www.soumu.go.jp/main_content/000731370.pdf)
- Immigrants at less risk of violent crime. Statistique Canada. (https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-402-x/2010000/chap/imm/imm02-eng.htm)
- Enhancing Community Policing with Immigrant Populations. NATIONAL SHERIFFS’ ASSOCIATION. (https://www.sheriffs.org/sites/default/files/cops-w0747-pub.pdf)
- 外国人との共生に関する意識調査(日本人対象). 出入国在留管理庁. (https://www.moj.go.jp/isa/support/coexistence/survey03.html)
- How Marco Rubio has shapeshifted to embrace Trump’s foreign policy. Al Jazeera. (https://www.aljazeera.com/news/2024/11/12/how-marco-rubio-has-shapeshifted-to-embrace-trumps-foreign-policy)