今年2月に始まった「財務省解体デモ」は、3月に入ってさらに広がりを見せ、大きな話題となっています。デモ参加者は様々な背景を持つ人々で構成されているようですが、共通の主張としては消費税の廃止または減税が挙げられています。私自身は、消費税率は当面10%のままとし、低所得者ほど負担が大きくなる「逆進性」の緩和については、給付付き税額控除(負の所得税)を導入し、その代わりに軽減税率を廃止すべきだと考えています。
消費税の問題については後日詳しく述べるとして、財務省を解体したとしても、予算の配分を担当する政府機関は絶対に必要です。そのため、「財務省解体」を叫ぶこと自体には妥当性を感じません。しかし、財務省解体を訴える人々の主張の背後には、財務省が日本経済全体の発展や国民の生活向上を目指すのではなく、税収の最大化を最優先しているという問題意識があります。この点については否定できません。本来、予算の配分は日本経済の発展や国民生活の向上を目指すべきであり、現在の財務省の行動原理がこれに反していることは、多くの人々が同意するのではないでしょうか。
財務省がなぜこのような組織になったのかというと、主に以下の2点が挙げられます。
- 財務省が歳入と歳出の両方を担当していること。
- 財務省の人事が、東京大学法学部出身者に偏重してきたため、経済学に精通した人材が重用されなかったこと。
①に関しては、諸外国でも、歳入を司る組織(日本では国税庁)は財務省の下部組織となっていますが、日本の国税庁は財務省からの独立性が非常に弱く、事実上支配されています。その結果、「徴税」と「予算編成権」が一体化し、財務省が国税の徴収権を持つことが批判されています。
②については、経済学に精通していない法律学専攻だった役人たちが財務省を運営してきたことが問題です。本来、予算編成では、経済成長を促進し、所得の不平等を減少させるための最適な予算配分が重視されるべきです。しかし、経済学の基礎的知識に欠けた人々が政策決定に関わる結果、わかりやすい「税収の最大化」が組織の目標として選ばれてしまっているのです。
では、どうすべきかというと、組織の再編と人事制度の見直しが必要です。まず、財務省内で「歳入」と「歳出」を担当する部門を完全に分離し、経済部門の省庁を再編するべきです。具体的には、かつて民主党が提唱したように、国税庁を財務省から分離し、社会保険料の徴収事務と統合して「歳入庁」を設立することが考えられます。また、財務省と内閣府の旧経済企画庁部門、経済産業省の経済政策局を統合し、経済・財政政策を担当する「経済財政省」を設立すべきだと考えます。
次に、人事制度に関しては、幹部候補生は、経済学の知識を大学院レベルで有し、かつ法律学や政治学にも精通した人材であるべきです。現在、日本の大学でダブルメジャー制度が採用されている大学は少数派ですが、この制度を全ての大学で導入するべきです。これにより、公務員試験という狭い枠にとどまらず、複数の分野に深い学問的知識を持った人材を育成できるようになります。
今日の日本経済の問題がすべて財務省の失敗に起因するとは思いませんが、財務省をはじめとする行政組織は見直しが必要な時期に来ていると感じます。私たちは、日本型大統領制や州制度の導入に加え、中央省庁の再編を訴えています。日本の政治・行政システムは金属疲労を起こしており、これを刷新することが日本の復活には不可欠だと思います。


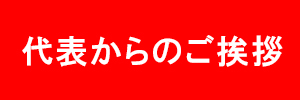

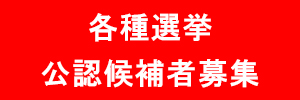


コメント